何のために古典はあるか?その意義は理解しつつも、無批判であるべからず?(幸福の科学)
こんにちは。
誰もが、小学生時代に歴史を学習しましたよね?
その時、疑問に思った人もいるでしょう。
なんで昔のことをいまさら学ぶ必要があるのだろうと?
また、中学に上がると、国語で古典を学びましたよね。
その時も、同じように疑問に思った人もいるでしょう。
なんで昔のことをいまさら学ぶ必要があるのだろうと?
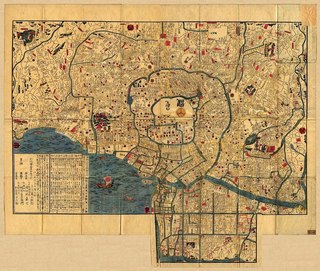
それは、昔のことから現代の人によっても学ぶべき点がいろいろあるからです。
昔の話しでも、その人物のモラルや行動、あるいは指針などについて、学ぶべき点があるからこそ教育に取りれられたのです。
その点を自ら、探そうという努力が受け手にも求められることは間違いないのです。
むかしのことだから〜といって、通り過ごしてはもったいないです。
そういうことを理解せずに、歴史を取り扱う大学での学問での「歴史学」において、その教科を担当する教授でも、人類の過去の話しをしているだけのパターンがあるのですが、それでは何のためにこの教授は大学の教員になったの?と疑問に思うこともありました。
歴史の意義がまるで理解できていなかったのです。

ただし、昔のことが何もかも学べることだらけというわけでもないのです。
古典は、いくら時代が降っても後世の人たちが学ぶ要素を含んだものをいうのであって、昔の文物がすべて古典とは言わないのです。
その意義が、その作品にあるかどうかは人によって変わってくるのは言うまでもないです。
ゆえに、それが古典、いやそれは古典ではないという論争が出てくるのは必然でしょう。
人類の過去から学ぶ。
こういうことを考えると、やはり思い浮かぶのは宗教についてでしょう。

私が思うのは、昔、ことに鎌倉時代の仏教を信仰する人の中で、当時の開祖の言ったことをそのまま信じ込んで、現代にも当てはめようとする人たちがいるということですね。
その宗教にぞっこんになってしまい、そうしたい気持ちはわからなくはないですが、きちんと現代社会との齟齬、嚙み合わせをしていくことが大事と思われてならないのです。
「この経文を唱えれば必ず快方に向かう」という開祖の言葉を信じて、その経文を必死に唱える。
それで満足してしまうのです。
実際に理想の形になったかどうか?
これにバイアスをかけるべきであって、開祖の言ったことを守ったかどうかではないのです。
昔の科学の発達していなかった時代においては、多くの人が「この経文を唱えれば必ず快方に向かう」と思うほかなかったこともあったでしょう。
ゆえに、そのことを非難するには及ばないのです。
しかし、現代では、それでは快方には向かわないということがわかったら、違う方法を試すべきであると思われてならないのです。
簡単なことなのですが、長年、そういう経文を唱えることで解決をしようとしてくると、そこから脱することが難しくなるのですね。

やはり人間だれしも、私含めて保守的なのです。
しかし、そこは勇気を出して、違う方法に切り替える必要があるのです。
人間関係でも一緒です。
例えば、人を貶したりすることで、マウントをとろうする人は古今東西いるものです。
なぜ、その人はそういう思考法になってしまうのか?
自尊心不足と経験値の不足なのです。
自尊心とは、自然体で自分を誇らしげに思える心というふうに定義するのがいいでしょう。
ゆえに自尊心がない人は、人を貶したり、上げ足取りをすることで自尊心をみたそうとするのです。
しかし、そんなものは偽物ゆえに、時間がたつとすぐに気落ちするのです。
そしてまた人を貶したりなじったりするのです。

こういう人が、そういう思考法から脱するにはどうすればいいか?
よく宗教に入っている人にはある疑問でしょう。
するとその宗教の人は、この経文を唱えれば必ずその人は変わる、といったニュアンスのことを言うのです。
しかし、その経文を唱えたところで、その人が変わることはないのです。
ではどうすればいいか?
その人が、格闘技をこなして強くなり、自信を身に着けることです。

その自信によって、人を貶したりすることが馬鹿ばかしくなって、やめるのです。
かくいう私もそうでした。
格闘技をすることで強くなり、自信がついて人をばかばかしくなってやめたのです。
貶そうと思ってもできなくなるのです。
しかし、鎌倉時代においては格闘技などなかったがゆえに、誰もがその偉大なる開祖の言われるままに経文を唱えたのでしょう。
しかし、それは叶わぬ夢だった。
そのことを頭に入れて生きていく必要があるでしょう。
その他、経文を唱えてもかなわないことはいくらでもありますから、それに縋るのではなく、合理的、論理的、科学的に考えて、同sればいいかを模索して、行動に移すことをお勧めしたいのです。
幸福の科学の故.大川隆法総裁(下写真)は、いにしえのいろんな宗教にの拠りつつも、現代的な科学的な方法をも取り入れて総合化をはかろうとしたのだろうと思います。

それは、私の支持したいスタンスゆえに、これまでいろんな総裁の本を読み、その意義を書いたブログをあげてきたのです。
幸福の科学というと、どうしても宗教性を排除した感じに思われるかもしれないですがそんなことはないのです。
宗教やスピリチュアルな面を基礎としながらも、科学的なものも取り入れて総合化を図り、現代情報にも素早くキャッチアップする。
そのスタンスには共鳴に値するスタンスと思いました。
単に仏や神に縋るという、その有用性について勉強するのならば、しておいた方がいいだろうことは間違いないでしょう。
宗教に入って、その宗教が刊行する雑誌や冊子だけを読んで行くのは、私としては支持できないですね。
自身でどんどん進んで情報をキャッチアップして取り入れて、それを日々の行動に結びつける、それが望ましいスタンスですわたしにとって。
現代においては、住宅は区画が敷いてあって、その区画内に家を建てています。
その住宅は、戸建てであろうと、集合住宅であろうと道に面する形になっています。
区画の真ん中に家を建てるということはほんの稀にしか行われないのです。
区画の中に家建てないのは風水的な根拠があって建てないのです。

何故か?
そういう家は不運を招くということがこれまでの人類の経験からわかっているからです。
ここに、そういうスピリチュアルな面が生きているのです。
宗教的なということもできるでしょう。
いくら科学が発達しても、スピリチュアルや宗教を抜きにして人生を歩んで行くことはできないのです。
それがわかった人には以下の電子書籍はおすすめです!
●以下よりどうぞ!
『比較;大川隆法論 非信者が論じる大川隆法氏の信憑性と天才性』
→Amazon Kindle
今回はこれにて終了します。
ありがとうございました!

 スポンサーリンク 1
スポンサーリンク 1
 スポンサーリンク 2
スポンサーリンク 2
幸福の科学の本紹介 ホーム
汗牛充棟.com ホーム
♯幸福の科学
♯鎌倉仏教
誰もが、小学生時代に歴史を学習しましたよね?
その時、疑問に思った人もいるでしょう。
なんで昔のことをいまさら学ぶ必要があるのだろうと?
また、中学に上がると、国語で古典を学びましたよね。
その時も、同じように疑問に思った人もいるでしょう。
なんで昔のことをいまさら学ぶ必要があるのだろうと?
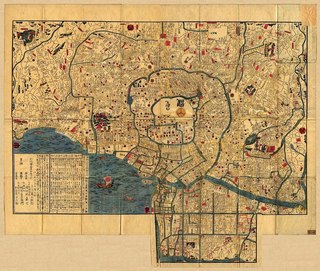
それは、昔のことから現代の人によっても学ぶべき点がいろいろあるからです。
昔の話しでも、その人物のモラルや行動、あるいは指針などについて、学ぶべき点があるからこそ教育に取りれられたのです。
その点を自ら、探そうという努力が受け手にも求められることは間違いないのです。
むかしのことだから〜といって、通り過ごしてはもったいないです。
そういうことを理解せずに、歴史を取り扱う大学での学問での「歴史学」において、その教科を担当する教授でも、人類の過去の話しをしているだけのパターンがあるのですが、それでは何のためにこの教授は大学の教員になったの?と疑問に思うこともありました。
歴史の意義がまるで理解できていなかったのです。

ただし、昔のことが何もかも学べることだらけというわけでもないのです。
古典は、いくら時代が降っても後世の人たちが学ぶ要素を含んだものをいうのであって、昔の文物がすべて古典とは言わないのです。
その意義が、その作品にあるかどうかは人によって変わってくるのは言うまでもないです。
ゆえに、それが古典、いやそれは古典ではないという論争が出てくるのは必然でしょう。
人類の過去から学ぶ。
こういうことを考えると、やはり思い浮かぶのは宗教についてでしょう。

私が思うのは、昔、ことに鎌倉時代の仏教を信仰する人の中で、当時の開祖の言ったことをそのまま信じ込んで、現代にも当てはめようとする人たちがいるということですね。
その宗教にぞっこんになってしまい、そうしたい気持ちはわからなくはないですが、きちんと現代社会との齟齬、嚙み合わせをしていくことが大事と思われてならないのです。
「この経文を唱えれば必ず快方に向かう」という開祖の言葉を信じて、その経文を必死に唱える。
それで満足してしまうのです。
実際に理想の形になったかどうか?
これにバイアスをかけるべきであって、開祖の言ったことを守ったかどうかではないのです。
昔の科学の発達していなかった時代においては、多くの人が「この経文を唱えれば必ず快方に向かう」と思うほかなかったこともあったでしょう。
ゆえに、そのことを非難するには及ばないのです。
しかし、現代では、それでは快方には向かわないということがわかったら、違う方法を試すべきであると思われてならないのです。
簡単なことなのですが、長年、そういう経文を唱えることで解決をしようとしてくると、そこから脱することが難しくなるのですね。

やはり人間だれしも、私含めて保守的なのです。
しかし、そこは勇気を出して、違う方法に切り替える必要があるのです。
人間関係でも一緒です。
例えば、人を貶したりすることで、マウントをとろうする人は古今東西いるものです。
なぜ、その人はそういう思考法になってしまうのか?
自尊心不足と経験値の不足なのです。
自尊心とは、自然体で自分を誇らしげに思える心というふうに定義するのがいいでしょう。
ゆえに自尊心がない人は、人を貶したり、上げ足取りをすることで自尊心をみたそうとするのです。
しかし、そんなものは偽物ゆえに、時間がたつとすぐに気落ちするのです。
そしてまた人を貶したりなじったりするのです。

こういう人が、そういう思考法から脱するにはどうすればいいか?
よく宗教に入っている人にはある疑問でしょう。
するとその宗教の人は、この経文を唱えれば必ずその人は変わる、といったニュアンスのことを言うのです。
しかし、その経文を唱えたところで、その人が変わることはないのです。
ではどうすればいいか?
その人が、格闘技をこなして強くなり、自信を身に着けることです。

その自信によって、人を貶したりすることが馬鹿ばかしくなって、やめるのです。
かくいう私もそうでした。
格闘技をすることで強くなり、自信がついて人をばかばかしくなってやめたのです。
貶そうと思ってもできなくなるのです。
しかし、鎌倉時代においては格闘技などなかったがゆえに、誰もがその偉大なる開祖の言われるままに経文を唱えたのでしょう。
しかし、それは叶わぬ夢だった。
そのことを頭に入れて生きていく必要があるでしょう。
その他、経文を唱えてもかなわないことはいくらでもありますから、それに縋るのではなく、合理的、論理的、科学的に考えて、同sればいいかを模索して、行動に移すことをお勧めしたいのです。
幸福の科学の故.大川隆法総裁(下写真)は、いにしえのいろんな宗教にの拠りつつも、現代的な科学的な方法をも取り入れて総合化をはかろうとしたのだろうと思います。

それは、私の支持したいスタンスゆえに、これまでいろんな総裁の本を読み、その意義を書いたブログをあげてきたのです。
幸福の科学というと、どうしても宗教性を排除した感じに思われるかもしれないですがそんなことはないのです。
宗教やスピリチュアルな面を基礎としながらも、科学的なものも取り入れて総合化を図り、現代情報にも素早くキャッチアップする。
そのスタンスには共鳴に値するスタンスと思いました。
単に仏や神に縋るという、その有用性について勉強するのならば、しておいた方がいいだろうことは間違いないでしょう。
宗教に入って、その宗教が刊行する雑誌や冊子だけを読んで行くのは、私としては支持できないですね。
自身でどんどん進んで情報をキャッチアップして取り入れて、それを日々の行動に結びつける、それが望ましいスタンスですわたしにとって。
現代においては、住宅は区画が敷いてあって、その区画内に家を建てています。
その住宅は、戸建てであろうと、集合住宅であろうと道に面する形になっています。
区画の真ん中に家を建てるということはほんの稀にしか行われないのです。
区画の中に家建てないのは風水的な根拠があって建てないのです。

何故か?
そういう家は不運を招くということがこれまでの人類の経験からわかっているからです。
ここに、そういうスピリチュアルな面が生きているのです。
宗教的なということもできるでしょう。
いくら科学が発達しても、スピリチュアルや宗教を抜きにして人生を歩んで行くことはできないのです。
それがわかった人には以下の電子書籍はおすすめです!
●以下よりどうぞ!
『比較;大川隆法論 非信者が論じる大川隆法氏の信憑性と天才性』
→Amazon Kindle
今回はこれにて終了します。
ありがとうございました!

幸福の科学の本紹介 ホーム
汗牛充棟.com ホーム
♯幸福の科学
♯鎌倉仏教
コメントを書く... Comments